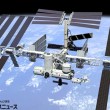ねつ造だったSTAP細胞。小保方晴子氏は手記で何を語るのか
今月28日、小保方晴子氏が講談社から手記『あの日』を出版した。世間を騒がせた「STAP細胞」騒動の真実はその手記の中でどこまで語られるのか注目が集まる。
スポンサーリンク2014年1月末、科学雑誌「Nature」でSTAP細胞の論文が公開されると、「世紀の発見」とともにその姿が日本中を駆け巡った。
かっぽう着を身につけ、実験用のピペットを持ちながら笑顔を振りまく小保方晴子氏。
明るいレモン色に塗られた研究室の壁を背景に、その笑顔が実によく映えていた。
若い女性の俊英の登場に、まるで日本中が祝福しているようだった。
しかし、2本の論文でデータの不正が疑われはじめると、事態はめまぐるしく展開する――。
論文の発表直後からネットではデータの不正が疑われていた。
最もインパクトが大きかったのは、論文にあるSTAP細胞由来の細胞の画像が、小保方氏の博士論文の画像データを酷似したことだ。
全く別の研究からのデータ“流用”を印象づけるには十分だった。
発表から1ヶ月に満たない2014年2月18日に、理研で調査委員会(石井俊輔委員長)が発足。
3月には共同研究者のひとり、山梨大学教授の若山照彦氏が、論文の撤回を呼びかけはじめる。
3月31日、調査委員会が画像データのねつ造と改ざんを認定すると、小保方氏は不服を申し立てた。
4月4日、理研は研究不正防止のための改革委員会(岸輝雄委員長)を設置した。
体調不良でそれまで公の場での発言がなかった小保方氏は、4月8日に会見を開き、STAP細胞の存在をアピール。
有名な「STAP細胞はあります」発言はここでのものだ。
混乱に拍車をかけたのは、理研や他の共同研究者たちの姿勢だった。
STAP細胞の論文に掲載されたデータや、研究資料の徹底的な調査に取り組まず、超一流の共同研究者たちが、なぜか論文のデータや保存された実験資料を見直すよりも、STAP細胞の存在証明に躍起になった。
一方、理研の研究不正防止のための改革委員会は6月12日に、小保方氏と共同研究者の多くが所属する、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(CDB)の解体とトップ交代にまで踏み込んだ提言を発表した。
その後もSTAP細胞探しは続く。
共同研究者であるCDBの丹羽仁史氏だけでなく、小保方氏も監視カメラのついた実験室でSTAP細胞の作製にトライしたが、結局はうまくいかない。
7月にようやく2本の論文が撤回された。
最悪の事態が起こったのは8月5日。
2本の論文の執筆に大きく関わった、CDB・笹井芳樹副センター長が自殺する。
2014年12月26日に理研の調査委員会(桂勲委員長)が、全てのSTAP細胞はES細胞だったとの結論を発表し、一応の終息を迎えた。
つまり、はじめからSTAP細胞は存在していなかったのだ。ここにたどり着くまで論文発表から11ヶ月が経っていた。
この調査報告でも別のデータねつ造が明らかになった。また、調査のために求められた、実験で得られた(はずの)オリジナルデータを小保方氏は提供していない。
トップの交代した理化学研究所発生・再生科学総合研究センターは、多細胞システム形成研究センターと名を変えたが、略称であるCDBはそのまま変わらなかった。
さて、小保方晴子氏は著書で何を語るのだろうか。
取材・文 山下 祐司
【了】